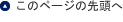判例紹介 No.19
知財高裁平成21年11月19日判決 平成21年(行ケ)10157号

1.事案の概要
特許権登録(請求項1〜7)→異議申立→特許取消決定(請求項1〜7)→第1次決定取消訴訟提起→訂正審判請求(請求項1〜7を訂正)→訂正拒絶理由通知→審判請求書の補正と意見書平成19年1月15日(請求項3,5,7を削除)→訂正不成立1次審決(補正は要旨変更につき認めない、請求項3,5,7は独立特許要件欠如)→審決取消1次訴訟提起→同1次判決平成20年5月28日(審決を取消す:原告は請求項1,2,4,6についての訂正を求める趣旨を特に明示したのだから、請求項3,5,7と分けて判断すべき)→別事件最高裁判決平成20年7月10日(異議申し立てに対する訂正請求は請求項ごとに判断する。訂正審判は一体不可分)→訂正不成立2次審決(別事件最高裁判決により訂正審判は一体不可分)平成20年9月17日→審決取消訴訟2次訴訟(本件訴訟)提起→同判決(2次審決を取消す)→訂正容認3次審決平成21年12月28日(平成19年1月15日手続補正書による請求項3,5,7の削除を認める)
2.1次判決理由の要点(平成19年(行ケ)第10163号)
平成19年1月15日付けでなされた訂正審判請求書の補正の内容は新請求項3・5・7を削除しようとするものであり,同日付け意見書にも新請求項1・2・4・6の訂正は認容し新請求項3・5・7の訂正は棄却するとの判断を示すべきであるとの記載もあることから,審判請求書の補正として適法かどうかはともかく,原告は,残部である新請求項1・2・4・6についての訂正を求める趣旨を特に明示したときに該当すると認められる。
そうすると,本件訂正に関しては,請求人(原告)が先願との関係でこれを除く意思を明示しかつ発明の内容として一体として把握でき判断することが可能な新請求項3・5・7に関する訂正事項と,新請求項1・2・4・6に係わるものとでは,少なくともこれを分けて判断すべきであったものであり,これをせず,原告が削除しようとした新請求項3・5・7についてだけ独立特許要件の有無を判断して,新請求項1・2・4・6について何らの判断を示さなかった審決の手続は誤りである。
3.争点
平成20年5月28日の第1次判決の確定後に言い渡された最高裁平成20年7月10日判決との関係で,平成20年9月17日の第2次審決が前記第1次判決の拘束力(行訴法33条1項:処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。)に反するか。最高裁判決により事情変更となったか。
4.関係する最高裁判決
(1)昭和55年5月1日第一小法廷判決(昭和53年(行ツ)第27号)
実用新案権の明細書の訂正審判の審理判断は、総ての訂正個所を一体不可分としてしなければならない。例外として、請求人において複数の訂正箇所のうちの一部の箇所についての訂正を求める趣旨を特に明示したときは,分けて行う。
(2)平成20年7月10日第一小法廷判決(平成19年(行ヒ)第318号 民集62巻7号1905頁)
特許異議申立に対する訂正審判の請求の審理判断は、当事者対立構造における攻撃防御の均衡を考慮して、請求項ごとに行うことを認めた件。訂正審判請求は、請求項ごとの取り扱いを定める規定が存在しないこと、一種の新規出願としての実質を有することに照らすと,複数の請求項を訂正する訂正審判請求は,全体を一体不可分のものとして取り扱うことが予定されているという見解を示した。
5.裁判所の判断
行訴法33条1項の定める拘束力を有する確定判決(第1次判決)がなされた後に別事件に関する最高裁の新たな法的見解が示されたからといって,当然に拘束力に影響を及ぼすと解することは困難であるのみならず,仮にこれを肯定する見解を採ったとしても,平成20年最高裁判決を被告主張のように解することもできない。すなわち,被告が事情変更の論拠とする平成20年最高裁判決は,前記のとおり,異議申立てに係る特許取消事件の審理中に特許権者側から対抗的になされた訂正請求に関する事案についてのものであり,その判示も,訂正不可分を主張する特許庁の見解を否定し,これを可分と解するとしたものである。そして,訂正審判請求の場合はこれを不可分と解するとした部分は,訂正審判請求については,その全体を一体不可分のものとして取り扱うことが予定されているとの原則的な取扱いについて判示したものであり,昭和55年最高裁判決(昭和53年(行ツ)第27号)に依ってなされた例外的な取扱いを認めるべき場合についての判示,すなわち,請求人において複数の訂正箇所のうちの一部の箇所についての訂正を求める趣旨を特に明示したときは,それぞれ可分的内容の訂正審判請求があるとして審理判断する必要がある,との判示を否定するものとは解されない。
このことは,平成20年最高裁判決が訂正審判請求に関する昭和55年最高裁判決を変更する趣旨を含まないことから明らかである。
そうすると,平成20年最高裁判決は,昭和55年最高裁判決に依ってなされた第1次判決(取消判決)の拘束力に何らの法的影響を及ぼすものではないことになるから,被告の主張は採用することができない。
6.3次訂正審決(訂正2006−39153)
平成19年1月15日付け手続き補正書により補正された訂正明細書のとおり訂正することを認める。
7.検討
本判決により、複数の請求項の訂正を請求する訂正審判において、一部の請求項が独立特許要件を欠くことで訂正拒絶理由を受けたときは、その請求項を手続補正書により削除し、残りの請求項の訂正を求める趣旨を意見書により明示すれば、残りの請求項について訂正の可否が審理判断されることになった。
過去の特許庁のプラクティスは、訂正審判および訂正請求の審理判断は、いずれも全体を一体不可分として行っていたが、最高裁判決および本件判決により、今後は下記のように行われるものと考えて良い。
(1)複数箇所を訂正する訂正審判の可否の審理判断は、原則として一体不可分として行うが、請求人が一部の箇所の訂正を求める趣旨を特に明示したときは、分けて行う必要がある(昭和55年最高裁判決)。訂正対象請求項のうちの一部の請求項についての訂正を求める趣旨を特に明示したときは、請求項ごとに判断する(本件判決)。
(2)複数の請求項を訂正する訂正請求の可否の審理判断は、請求項ごとに行う(平成20年最高裁判決)。

 日本語
日本語 English
English