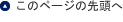判例紹介 No.08

1. 事実関係
(1)特許庁における手続き
原告は、平成6年8月26日に特許出願し平成15年6月20日に設定登録を受けて特許権者となった(本件特許)。本件特許に対し特許異議申立がなされ、原告は請求項1〜4にそれぞれa,b、c、dの訂正事項(aは特許請求の範囲の減縮、c、dは誤記の訂正)を加える訂正請求した。特許庁は、「訂正は認められない、請求項1ないし4に係る特許を取り消す。」と決定した。その理由は、①本件発明2を訂正する訂正事項bが,特許請求の範囲の減縮,誤記又は誤訳の訂正,明りょうでない記載の釈明のいずれを目的とするものでなく,また,特許請求の範囲を実質上拡張するものであるから,平成6年法律第116号による改正前の特許法126条1項ただし書又は2項により認められない、②本件発明2は引用発明に基づき容易に発明できたものである、であった。
(2)原告主張の決定取り消し事由
本件決定は,訂正事項bが不適法であることを理由に,他の訂正事項a,c,dについて何ら判断することなく訂正を認めなかったものであり,訂正事項a,c,dに関する訂正要件の判断を遺漏した違法がある。
(3)原判決(知財高裁平成18年(行ケ)10314号)
下記の理由により原告の請求を棄却した。
願書に添付した明細書又は図面の記載を複数箇所にわたって訂正することを求める訂正審判の請求又は訂正請求において,その訂正が特許請求の範囲に実質的影響を及ぼすものである場合には,請求人において訂正(審判)請求書の訂正事項を補正する等して複数の訂正箇所のうち一部の箇所について訂正を求める趣旨を特定して明示しない限り,複数の訂正箇所の全部につき一体として訂正を許すか許さないかの審決又は決定をしなければならない(最高裁昭和55年判決参照)。そしてこの理は,改善多項制の下でも同様に妥当する。
2. 最高裁判決
主文:1. 原判決のうち,請求項1に係る特許の取消決定に関する部分を破棄する。2.特許庁がした異議決定のうち、請求項1に係る特許を取り消した部分を取り消す。理由は下記参照。
(1) 特許法は,一つの特許出願に対し,一つの行政処分としての特許査定又は特許審決がされ,一つの特許権が発生するという基本構造を前提としており,請求項ごとに個別に特許が付与されるものではない。このような構造に基づき,複数の請求項に係る特許出願であっても,当該特許出願の全体を一体不可分のものとして特許査定又は拒絶査定をするほかなく,可分的な取扱いは予定されていない。一方で,特許法は,一定の場合には,特に明文の規定をもって,請求項ごとに可分的な取扱いを認める旨の例外規定を置いている(特許法185条のみなし規定のほか,特許法旧113条柱書き後段が「二以上の請求項に係る特許については,請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる。」と規定する,特許法123条1項柱書き後段も同趣旨)。
(2)訂正審判に関しては,請求項ごとに可分的な取扱いを定める明文の規定が存しない上,訂正審判請求は一種の新規出願としての実質を有すること(特許法126条5項,128条参照)にも照らすと,複数の請求項について訂正を求める訂正審判請求は,全体を一体不可分のものとして取り扱うことが予定されているといえる。
これに対し,特許法旧120条の4第2項の規定に基づく訂正の請求は,特許異議申立事件における付随的手続であり,独立した審判手続である訂正審判の請求とは,特許法上の位置付けを異にするものである。本件訂正のように特許異議の申立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とするものについては,いわゆる独立特許要件が要求されない(特許法旧120条の4第3項,旧126条4項)など,訂正審判手続とは異なる取扱いが予定されており,訂正審判請求のように新規出願に準ずる実質を有するということはできない。そして,特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正請求は,請求項ごとに申立てをすることができる特許異議に対する防御手段としての実質を有するものであるから,各請求項ごとに個別に訂正を求めるものと理解するのが相当であり,また,各請求項ごとの個別の訂正が認められないと,特許異議事件における攻撃防御の均衡を著しく欠くことになる。
以上の諸点にかんがみると,特許異議の申立てについては,各請求項ごとに個別に特許異議の申立てをすることが許されており,各請求項ごとに特許取消しの当否が個別に判断されることに対応して,特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正請求についても,各請求項ごとに個別に訂正請求をすることが許容され,その許否も各請求項ごとに個別に判断されるものと考えるのが合理的である。
被上告人は,発明を表現する明細書は常にその全体が一体不可分のものとして把握されるべきであると主張するが,昭和62年法律第27号による特許法の改正により,いわゆる一発明一出願の原則を定めていた規定が削除され,しかも一発明に複数の請求項の記載をすることが認められるようになったことを考えると,同改正後の特許法の下で,上記のように解すべき根拠を見いだすことはできない。最高裁昭和55年5月1日第一小法廷判決は,複数の請求項を観念することができない実用新案登録請求の範囲中に複数の訂正事項が含まれていた訂正審判の請求に関する判断であり,本件のように,複数の請求項のそれぞれにつき訂正事項が存在する訂正請求において,請求項ごとに訂正の許否を個別に判断すべきかどうかという場面にまでその趣旨が及ぶものではない。
(3) 以上の点からすると,特許異議申立事件の係属中に複数の請求項に係る訂正請求がされた場合,特許異議の申立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正については,訂正の対象となっている請求項ごとに個別にその許否を判断すべきであり,一部の請求項に係る訂正事項が訂正の要件に適合しないことのみを理由として,他の請求項に係る訂正事項を含む訂正の全部を認めないとすることは許されない。
3. 検討
訂正審判請求及び訂正請求の訂正の許否についての特許庁の実務は、複数の訂正事項の全体を一体不可分なものとして判断していた。
本件最高裁判決は、訂正請求については、当事者対立構造における攻撃防御の均衡を考慮し、各請求ごとに個別に判断しなければならないとして特許庁の実務を否定し、他方、訂正審判請求については、新規出願に準ずる実質を有することを考慮して、特許庁の実務を肯定したものである。攻撃防御の均衡を考慮したという判決理由は、当事者系である特許無効審判での訂正請求にはそのまま当てはまるが、当事者系というより査定系に近い特許異議申立での訂正請求については疑問である。

 日本語
日本語 English
English